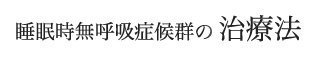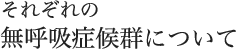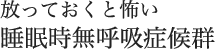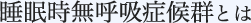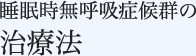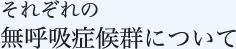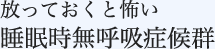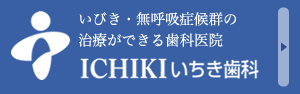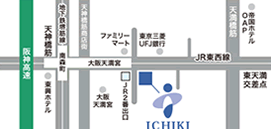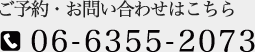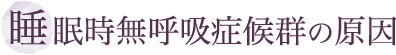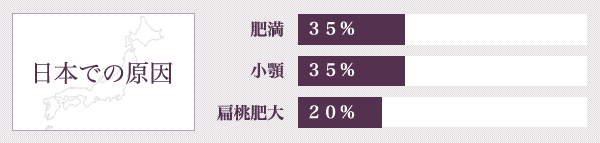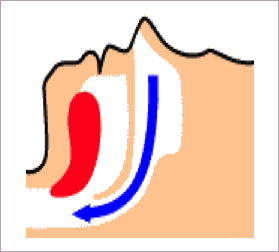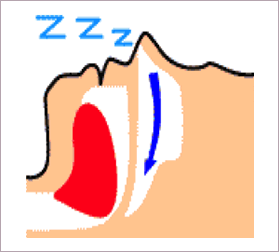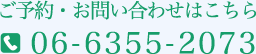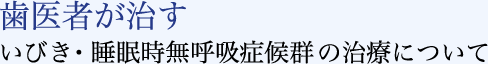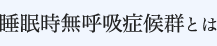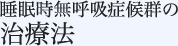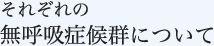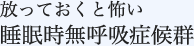1956年に初めて眠気を伴い、治療すべき病気だとして睡眠時無呼吸症候群が報告されました。
わかりやすい症状としては毎日イビキがうるさいことや睡眠時間を十分とっていても眠いということがあります。イビキをかいていたと思うと急に息が止まり、その後カッと音がして苦しそうに息をしていると周りの人から言われると正に睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いです。寝ている間に呼吸ができずに急に死んでしまうことはありません。呼吸ができなくなって血液中の酸素濃度が低くなると脳は寝ている状態から覚醒させて呼吸を復活させるからです。そのため、寝ては起こされるという状態を繰り返しています。睡眠の質が悪いために慢性的な睡眠不足状態になります。ですから、いつも睡眠が足りていないので、寝付きが良く、本人は睡眠の質が悪いとは認識していないことが多いです。このような症状を感じたことがある方や指摘された方は一度調べられることをお勧めいたします。睡眠の質の低下から学習能力と労働能力の低下が見られることが報告されています。
日本でのイビキをかく人は2000万人、睡眠時無呼吸症候群の推定患者は300万人と言われており、癌や脳梗塞、糖尿病の患者数より多いのです。しかし、社会的にはあまり認知されておらず、ただのいびきと放置されている場合があります。2003年に新幹線の運転士が居眠りで停車駅を通過したことで、ニュースで取り上げられ、初めてこの病気の名前を聞いた方がほとんどではないでしょうか?
基本的には太っている方がなりやすいのですが、欧米人に比べて東洋人は顎が小さいため、太っていなくても(BMI25以下)睡眠時無呼吸症候群と診断される方が3割ほどおられます。骨の大きさと舌の大きさのバランスで調べると患者と健常者では相関が見られます。欧米人はBMI32以上、東洋人はBMI27以上で重症化しやすいことがわかっています。 年寄りの方は10~20%の頻度で無呼吸があります。

・大きないびき
・睡眠中の多動
・夜間の頻尿
・夜尿症
・熟睡感の欠如
・性格の変化
(イライラする、キレやすい、うつなど)
・夜間の寝汗
・夜間の咳
・睡眠中の窒息感、息切れ、あえぎ呼吸
・早朝の頭痛
・性機能低下(男性、ED)
・不眠
・日中の強い眠気、倦怠感、集中力の欠如
・歯ぎしり
・ドライマウス