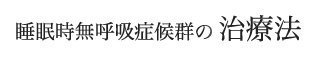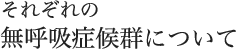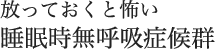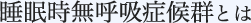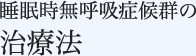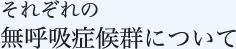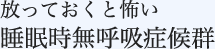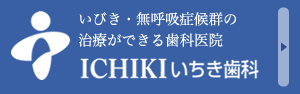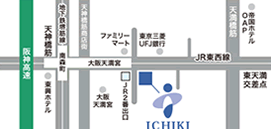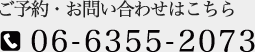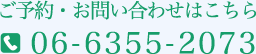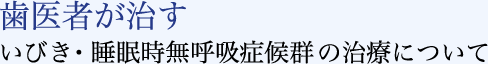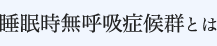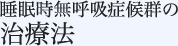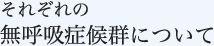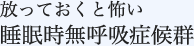居眠り
睡眠時無呼吸症候群の危険性として、マスコミで報道されたように居眠りがあります。居眠り事故による死亡の可能性が高まります。
全身的な影響
軽度でも高血圧になりやすく、3割の患者に高血圧があり、3割の高血圧患者に無呼吸があります。
肥満になりやすくなる
代謝異常により(レプチン抵抗性 食欲抑制できない)(グレイン亢進 食欲増進)(インスリン亢進 太りやすくなります)。
勃起不全になりやすくなる
心疾患系、脳血管系のリスクを高める
糖尿病と同じくらい循環器系合併症の危険因子となります。冠動脈狭窄の35%が無呼吸患者です。 うっ血性心不全 不整脈 虚血性心疾患 脳血管障害を起こすリスクが高まります。
自律神経への影響
寝ている間は副交感神経が優位に働きますが、起こされるために交感神経が活性化して自律神経のバランスを崩します。
無呼吸を放置すると12年後に4割以上の睡眠時無呼吸症候群の患者は心筋梗塞や脳卒中を起こし、これらの原因で寿命を縮めることになります。その他として糖尿病、腎臓病、不整脈、胃食道逆流症などの合併症が高い確率で発生します。
睡眠時無呼吸症候群の生存率


仕事としてトラック、バス、タクシー、鉄道、船、飛行機など運転する人は、日本には300万人以上もおります。肥満の人や男性は、睡眠時無呼吸症候群を発症しやすい傾向にありますが、職業運転者には肥満傾向の男性が多く、睡眠時無呼吸症候群の発症リスクが高いとされています。しかも発症リスクが高いのに職業運転者は睡眠時無呼吸症候群の自覚症状が乏しい傾向にあります。過去にトラック
運転者2万人に対しておこなった大規模な調査では、中~重症の睡眠呼吸障害があると診断されたトラック運転者の86%が、眠気などの自覚症状に乏しいという結果がでました。

AHI(1時間当りの無呼吸および低呼吸の回数)が10以上で居眠り事故を起こす確率は6.3倍になります。多くの研究により、睡眠時無呼吸症候群の患者さんは、健常者よりも交通事故を引きおこす確率が高いことがわかっています。運転者の眠気を原因とする事故は、事故全体の10~30%を占めるとされています。
バスやトラックや車の居眠り運転事故は、ブレーキをふまないまま発生することが多いため、致死率が高い大きな事故になりやすい傾向にあります。
アメリカでの運転記録による実態調査では、睡眠時無呼吸症候群の患者さんの交通事故発生率は、健常者の約7倍も高いとのことです。交通事故の発生率が高いのは、いびきや無呼吸によって睡眠の質が悪い結果、運転中に寝てしまったり、うとうとしてしまったり、注意力が低下するためです。同様の調査結果は、日本、カナダ、スペインなど世界各国から多数報告されています
1979年のスリーマイル島の原子力発電所炉心融解未遂事故
1986年のスペースシャトルの発射直後の爆発事故
1989年のアラスカ沖のタンカー座礁(史上最悪のタンカー事故)
日本における睡眠障害による経済損失は、医療費を含まない額で年3.5兆円と試算されています。

ふだんから十分睡眠をとり、睡眠不足が生じないように、規則正しい生活習慣を心がけましょう。
睡眠時無呼吸症候群であれば、適切な治療をおこないましょう。
眠たくなったら、短時間(15~30分程度)の仮眠をとるようにします。30分以上の仮眠をとると、眠気がとれなくなることがあるので注意が必要です。
仮眠後は、身体を動かして十分覚醒させましょう。起きてすぐはまだ眠たさが残っています。コーヒーなどのカフェイン飲料を上手に摂取しましょう。ただし、カフェインの効果が現れるのは、摂取してから30分後くらいです。また、糖分の入ったカフェイン飲料の大量摂取は、肥満や睡眠時無呼吸症候群の症状悪化になるので注意が必要です。
ガムを食べたり、声を出したりしてアゴを運動させると、脳が活性化します。